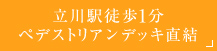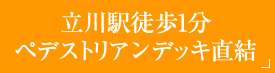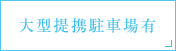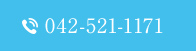こんにちは🌷
立川駅前こばやし内科・胃と大腸内視鏡クリニックです🏥✨
まだまだ寒い時期が続いていますが、みなさん体調お変わりなく過ごされておりますでしょうか?🌸少し気が早いお話ですが、暖かくなるとお花見や歓迎会などお酒を飲む機会も増えてくる時期ですね🍺そんな時期が本格到来する前にアルコールが及ぼす体への影響についてお話したいと思います☝🏻
耳が痛くなるお話かもしれませんが、肝臓とアルコールの関係性を中心に、後半ではアルコールを飲むと顔や皮膚が赤くなったり心臓がドキドキするという方へのお話もいたしますので、本格お花見シーズン到来の前にぜひこちらのブログを最後まで読んでみてください‼️
🍺肝臓とアルコール🍺
肝臓はアルコールの代謝において重要な役割を果たしています🚑アルコールを摂取することは肝臓に一定の負担をかけ、過剰摂取が肝機能に深刻な影響を及ぼす可能性があります⚠️
肝臓とアルコールの関係について詳しく説明いたします。
①アルコールの代謝
アルコール(エタノール)は肝臓で主に代謝されます。肝臓内でアルコールは酵素によって分解され、最終的に無害な物質(アセテート)に変わります。この代謝過程では主に以下の酵素が関与しています!
・アルコール脱水素酵素(ADH)→アルコールをアセトアルデヒドに分解します。
・アルデヒド脱水素酵素(ALDH)→アセトアルデヒドを酢酸に変換します。
・ミクロソームエタノール酸化系(MEOS)→大量のアルコール摂取時に働く補助的な経路です。
アルコールは肝臓で代謝されるとき、アセトアルデヒドという中間産物が生成されます。アセトアルデヒドは毒性が強いため、これを素早く分解することが肝臓にとって重要です🩺しかし、大量のアルコールを短期間で摂取すると、この代謝過程が追いつかず、アセトアルデヒドが体内に蓄積し、肝臓や他の臓器にダメージを与える可能性があります・・・⚡️
②アルコールと肝障害
アルコールの摂取が続くと、肝臓にさまざまな影響を及ぼし、以下のような肝障害を引き起こすことがあります!
・脂肪肝(アルコール性脂肪肝)
初期の段階では、肝臓に脂肪が蓄積します。これは「脂肪肝」と呼ばれ、アルコールの摂取量が多いほど発生しやすくなります。脂肪肝自体は無症状ですが、進行すると肝機能が低下することがあります。
・アルコール性肝炎
アルコールが長期間にわたって過剰に摂取されると、肝臓に炎症が生じることがあります。この炎症が進行すると、肝細胞が壊れ、肝臓の機能が低下します。症状としては、黄疸、腹痛、食欲不振、倦怠感などが現れることがあります。
・肝硬変
長期的なアルコール摂取は肝臓に線維化を引き起こし、最終的に肝硬変に進行することがあります。肝硬変は肝臓の正常な構造が崩れ、機能が低下する病態です。肝硬変が進行すると、肝不全や肝臓がんのリスクが高まります。
・肝臓がん(肝細胞癌)
長期間にわたるアルコールの過剰摂取が肝硬変を引き起こし、肝臓がんのリスクを増加させることが知られています。アルコール自体が発がん物質として作用する可能性もあります。
③アルコールの摂取と肝臓の回復
肝臓はある程度の回復能力を持っています👆軽度の脂肪肝や初期のアルコール性肝炎では、アルコールの摂取を中止することで肝臓が回復することが可能です。しかし、肝硬変や高度な肝障害が進行した段階では、肝臓の回復は難しくなるため、早期の段階での対応が非常に重要です⚠️
④アルコールの適量
アルコール摂取量の適正範囲を守ることが肝臓を守るために非常に重要です。日本で推奨されている飲酒量は以下のようになっております。
・男性:1日に純アルコール換算で約20g(ビールなら約500ml、ワインなら約200ml、焼酎なら約60ml程度)
・女性:1日に純アルコール換算で約10g(ビールなら約250ml、ワインなら約100ml、焼酎なら約30ml程度)
定期的にこれを超える飲酒を続けると、肝臓に深刻な負担がかかります!⚡️過度の飲酒は肝臓に深刻なダメージを与えるため、適度な飲酒を心掛けることがとても重要です🌼
⑤肝臓を守るための対策
・適量の飲酒🍻
過度な飲酒を避け、週に何日かは飲まない日(休肝日)を設けることが肝臓を守るために重要です。
・アルコールの種類を工夫する✨
アルコールを摂取する場合、ビールやワインなど、比較的アルコール度数の低いものを選ぶと負担を減らすことができます。
・食事と生活習慣の改善🍚
栄養バランスの取れた食事や規則正しい生活を心掛けることで、肝臓の健康をサポートします。
・定期的な健康チェック🏥
アルコール摂取量が多い場合、定期的な肝機能の検査を受けることが重要です。当院では採血や腹部エコーで肝臓の状態を評価します。
💡まとめ💡
アルコールは肝臓に大きな負担をかける可能性があり、過剰摂取は脂肪肝、肝炎、肝硬変、肝臓がんなどの重大な肝疾患を引き起こす原因となります😱適切な飲酒量を守り、生活習慣を整えることが肝臓の健康を守るために非常に重要です🍀
🍺アルコールを飲むと顔が赤くなる人は食道がんのリスクが高い?!🍺
アルコールを飲むと顔が赤くなる人は、アルコールの代謝に関わる酵素の働きに遺伝的な違いがある人々です。これには主に、アルコール脱水素酵素(ADH) と アルデヒド脱水素酵素(ALDH) の活性が関係しています。
①顔が赤くなる理由
アルコールを摂取すると、肝臓でアルコールはまず アルコール脱水素酵素(ADH) によってアセトアルデヒドに分解されます。アセトアルデヒドは非常に毒性が強いため、さらに アルデヒド脱水素酵素(ALDH) によって無害な酢酸に変換されます。この代謝過程において、ALDH2という酵素の働きが特に重要です。
ALDH2の活性が低い(または欠損している)方は、アルコール摂取後にアセトアルデヒドが体内に蓄積しやすくなります。アセトアルデヒドは血管を拡張させ、顔や皮膚が赤くなる原因となります。また、アセトアルデヒドは、顔や皮膚の赤みだけでなく、動悸や頭痛、吐き気などの不快な症状も引き起こすことがあります。病院で使用するアルコール綿で皮膚が赤くなるという方も同じ原理です。
この遺伝的なALDH2の活性の低さは、主にアジア系の人々に多く見られ、約30〜50%のアジア人はこの遺伝子変異を持っており、アルコールを飲んだ際に顔や皮膚が赤くなったり心臓がドキドキしたり不快な症状がでやすいです。
一方、欧米人を含む多くの人々は、この酵素が活発で、アルコールを効率的に分解できる人はアルコールで顔や皮膚が赤くなることはありません。
②リスク
アルコールを飲んで顔が赤くなる人にはいくつかの健康リスクが考えられます!
・アセトアルデヒドの蓄積による毒性⚠️
アセトアルデヒドは強い毒性を持っており、長期間にわたって高い濃度で体内に蓄積されると、肝臓や他の臓器に対するダメージが蓄積される可能性があります。このため、顔や皮膚が赤くなる人は、アルコール摂取が肝臓やその他の臓器に悪影響を与えやすい状態にあると考えられます。
・肝臓疾患のリスク増加⚠️
アルコールを摂取するたびにアセトアルデヒドが蓄積されるため、アルコール性肝疾患(脂肪肝、アルコール性肝炎、肝硬変)のリスクが増加します。ALDH2活性が低い人は、アルコール摂取量が少なくても肝臓に過剰な負担をかけることになりやすいです。
・がんのリスク⚠️
アセトアルデヒドは、発がん物質としても知られており、アルコールを摂取して顔が赤くなる人々は、口腔、食道、喉頭、肝臓などのがんのリスクが増加する可能性があります。特に、アジア系の人々は、ALDH2の活性が低い人が多いため、このリスクが高くなるとされています。つまりお酒で顔が赤くなる人は赤くならない人よりも飲酒によるがんのリスクが高いということなのです!!
・心血管系への影響⚠️
アセトアルデヒドは血管を拡張させる作用を持ち、これによりアルコール摂取後に顔が赤くなることが多いです。長期的にアセトアルデヒドにさらされると、高血圧や心血管疾患のリスクが高まる可能性があります。
③注意すべき点
・過度な飲酒は避ける👆
アルコール摂取後に顔や皮膚が赤くなる人は、体内でアセトアルデヒドが処理されにくいため、アルコールの摂取は控えめにすることが推奨されます。
・飲酒を避けることも選択肢👆
アルコール摂取による体調不良や健康リスクを避けるために、アルコールを摂取しないことも有効な選択肢です。ノンアルコール飲料の活用も有効ですね。
・医師に相談する👆
アルコールの摂取に関して不安がある場合は、医師と相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
💡まとめ💡
アルコールを飲んで顔が赤くなるのは、主にアセトアルデヒドの蓄積が原因です!
この状態は、特にALDH2の活性が低い人々に見られ、アルコール摂取が肝臓やがん、心血管系に対するリスクを高める可能性がございます。過度な飲酒は避け、健康リスクを最小限に抑えるためには、アルコール摂取量に注意することが重要です!
いかがでしたでしょうか?「酒は飲んでものまれるな」という言葉があるように、個々に応じた適度な飲酒量を守り、楽しい時間をすごしたいものですね✨
当院では知識・経験ともに豊富な肝臓専門医も複数名在籍しておりますので、肝機能で心配なことやそのほかの消化器疾患でお困りのことがありましたらどうぞ気軽にご相談くださいませ*
肝臓とアルコール🍻アルコールで顔が赤くなる人必見‼️⚠️赤くならない人よりがんのリスクが高い❓⚡️
2025.03.19