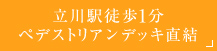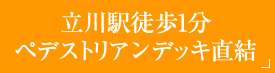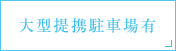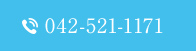こんにちは☀️
立川駅前こばやし内科・胃と大腸内視鏡クリニックです🏥✨
魚介類を食べた後に激しい腹痛や嘔吐に襲われる「アニサキス症」。
最近では、芸能人やスポーツ選手がアニサキス症になったニュースが報じられることもあり、一般の人々にも広く知られるようになりました。
しかし、「アニサキスって何?」「生魚を食べたら必ず感染するの?」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?👆
この記事では、アニサキス症の原因、症状、予防法、治療法などについて詳しく解説いたします。
魚介類を安心して楽しむためにも、ぜひ最後まで読んでみてください❗
アニサキスとは、寄生虫(線虫)の一種で、主にサバ、アジ、イカ、サンマ、タラ、サケなどの魚介類に寄生しています。特にサバに寄生するケースが多く、日本ではアニサキス症の原因の約6割がサバによるものと言われています🐟
アニサキスの幼虫(3期幼虫)は、魚の内臓に寄生していますが、魚が死ぬとすぐに筋肉(身の部分)へ移動します。そのため、鮮度が落ちた魚ほど、身の部分にアニサキスが多くなる傾向があります。
⚠️アニサキスの特徴
体長:2〜3cm程度
色:白色または半透明
形状:細長く、糸のような形
スーパーで買った魚の刺身や自分で捌いた魚に、白い糸のようなものが見えたら、それはアニサキスの可能性があります⚡️
⚠️アニサキスの生態と感染経路
アニサキスは、海洋生物の体内を巡る食物連鎖を通じて広がります。
①アニサキスの卵は海中に放出され、オキアミ(小型の甲殻類)が摂取
②オキアミを食べた魚介類(サバ・イカなど)に寄生し、幼虫として成長
③魚を食べた海洋哺乳類(クジラ・イルカなど)で成虫になり、繁殖
④クジラ・イルカの糞とともに卵が海中へ → 再び食物連鎖に戻る
本来、アニサキスは人間の体内では成虫になれませんが、間違って生きた幼虫を食べてしまうと、胃や腸の壁に侵入し炎症を引き起こすのです。
アニサキス症の発生件数は年々増加傾向にあり、2019年には336件の届出がありました。しかし、実際には年間2,000~3,000件の症例が発生していると推定されています😱
⚠️アニサキス症の症状
アニサキス症の症状は寄生虫が消化管内で動き回ることによって引き起こされます。
次のような症状が現れることがあります。
・腹痛
通常は食後数時間以内に発症し、特に右下腹部に痛みが現れることが多いです。
・嘔吐
アニサキスが消化管に侵入することによって、嘔吐が引き起こされることがあります。
・発熱
まれに軽度の発熱を伴うことがあります。
・アレルギー反応
まれにアニサキスに対してアレルギー反応を示すことがあります。
皮膚に発疹やかゆみが現れることもありますが、これは一般的な症状ではありません。
アニサキスが腸内で動くことにより、腹痛が引き起こされ、腸管に強い刺激を与えるため、急な腹痛が特徴的です。この痛みは、アニサキスが胃壁や腸壁を突き破ろうとする際に引き起こされます⚡️
👆診断
アニサキス症の診断は、症状と食歴(生魚や生の海産物を食べたことがあるかどうか)に基づいて行われます。
1️⃣内視鏡検査は、アニサキス症の診断において非常に重要です。内視鏡を使って消化管内を直接観察することで、アニサキスが胃壁や腸壁に寄生しているのを確認できます。アニサキスは透明で細長い形状をしているため、内視鏡での視覚的確認が可能です。
2️⃣CT検査や腹部超音波検査は、アニサキスが消化管内に侵入したことで引き起こされる異常を検出する手段として使用されることがあります。アニサキスが消化管内に寄生している場合、腸の壁が膨張している様子が確認できることがあります。
3️⃣血液検査では生虫に対する免疫反応を示す 抗体検査 を行うことで、感染を確認することができます。
👆治療
アニサキスによる腹痛が確認された場合、内視鏡を使ってアニサキスを取り除くのが最も一般的な治療法です。内視鏡でアニサキスを直接取り除くことにより、症状が改善されます。軽度の症例では、症状が自然に改善することもありますが、重篤な場合は外科的処置が必要となることもあります。軽度の症状の場合、薬物療法が使用されることがあります。痛みを和らげるために 鎮痛剤 や 消炎薬 が処方されることがあります。これにより症状の軽減が期待されます。まれに、アニサキスが消化管に深く侵入し、内視鏡では取り除けない場合、外科的手術が必要となることがあります。
👆予防
❶アニサキスを防ぐための基本ルール
アニサキスを無害化する方法は、「加熱」「冷凍」「目視確認」「内臓の適切な処理」の4つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう💁♀️
①加熱
アニサキスは、60℃以上で1分間の加熱で死滅します。
焼き魚・煮魚・フライなど、しっかり加熱すればアニサキス症のリスクはゼロになります。
✅ 安全な加熱調理のポイント
・焼き魚
中まで火が通るように十分加熱する(目安:80℃以上)
・煮魚
しっかり煮込む(沸騰した状態で5分以上)
・揚げ物
衣の中まで火が通るように170℃以上で揚げる
🔥半生やレアな調理法は危険!
「たたき」「炙り」「低温調理」は、アニサキスが生き残る可能性があるため注意が必要です。
②冷凍
アニサキスは-20℃以下で24時間以上冷凍すると死滅します。
そのため、市販の冷凍魚(適切に冷凍処理されたもの)は安全に食べられます。
✅ 家庭での冷凍保存のポイント
・-20℃以下で24時間以上冷凍(一般家庭用冷凍庫は-18℃なのでやや不十分)
・すぐに食べない場合は、購入後すぐに冷凍
・解凍後はすぐに食べる(時間が経つと細菌が繁殖する)
❌ 冷凍してもすぐには安全にならない
・短時間の冷凍(-18℃で数時間など)は効果なし
・冷蔵(0℃〜5℃)ではアニサキスは生き続ける
③目視確認〜アニサキスを探して除去〜
アニサキスは白い糸のような形をしているため、注意深く確認すれば発見できます。
特に、生で食べる場合は目視確認が必須です。
✅ 目視確認のポイント
・魚の身に白い糸状の虫がいないかチェック
・光を当てると発見しやすい
・包丁で身を細かく切ると見つけやすい
・刺身を食べる前にもう一度確認する
🐟特にサバ、アジ、イカ、サンマ、タラ、サケなどの魚は、目視確認を徹底しましょう!
④内臓の適切な処理
アニサキスは主に魚の内臓に寄生しているため、新鮮なうちに内臓を取り除くことが重要です。
魚が死んで時間が経つと、アニサキスは内臓から身へ移動するため、すぐに処理することがリスク低減につながります。
✅ 安全な内臓処理の手順
①魚を購入後、すぐに内臓を取り除く
②内臓を捨てる際はビニール袋に入れ、密封する
③まな板や包丁をしっかり洗う
④手をよく洗う(寄生虫が付着するリスクを防ぐ)
❷生魚を安全に食べるための注意点
刺身や寿司を安全に楽しむためには、新鮮な魚を選び、適切に処理することが大切です。
✅ 生魚を安全に食べるポイント
・冷凍処理された魚を選ぶ(-20℃以下で24時間以上冷凍済み)
・鮮度の良い魚を選ぶ(目が澄んでいて、身がしっかりしている)
・専門店(信頼できる鮮魚店やスーパー)で購入する
・調理時に目視で確認し、異常があれば食べない
・食べる直前に切る(鮮度を保つ)
❌ 危険な食べ方
・釣った魚をそのまま生で食べる
・冷蔵庫で保存しすぎた魚を生で食べる
・ワサビや酢で処理して安心する(アニサキスは死なない)
⚠ ワサビや酢、醤油、塩ではアニサキスは死にません!
・「酢締め」「ワサビをたっぷりつける」は効果がないので要注意です。
❸アニサキス症を防ぐための魚料理の具体例
安全に食べるための調理法を具体的に紹介します。
|
料理 |
アニサキス対策 |
|
焼き魚(サバ・ホッケなど) |
完全加熱(60℃以上で1分以上)🐟 |
|
煮魚(ブリ大根・カレイの煮付け) |
しっかり火を通す(5分以上沸騰) |
|
天ぷら・フライ(アジ・キスなど) |
170℃以上でカラッと揚げる🍤 |
|
寿司・刺身(マグロ・サーモン) |
冷凍済みの魚を使用、目視確認🍣 |
|
しめサバ(酢締め) |
冷凍済みのものを使う(酢だけでは効果なし) |
アニサキス症を防ぎ、安全に魚を食べるためには、以下のポイントを押さえましょう。
✅ 加熱調理(60℃以上で1分)で確実に殺す
✅ -20℃以下で24時間以上冷凍すれば安全
✅ 目視確認でアニサキスを除去する
✅ 内臓をすぐに取り除き、身への移動を防ぐ
✅ ワサビや酢、醤油ではアニサキスは死なない!
安全な処理を徹底すれば、刺身や寿司も安心して楽しめます!😊
アニサキス症は、日本において比較的よく見られる食中毒の一つです。生魚を食べる文化があるため、感染のリスクは避けられませんが、適切な処理や注意を払うことで予防が可能です。安全に魚介類を楽しむためにも、冷凍や加熱処理、内臓の早期除去を意識しましょう!
魚介類を食べた数時間後に激しい胃痛が発生した、食後1日以内に強い下腹部痛や腸の張りを感じる、吐き気や嘔吐などの症状がある場合はお気軽に当院へご相談くださいませ🍀