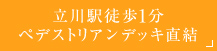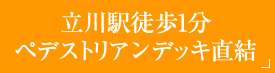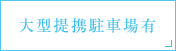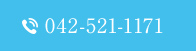こんにちは🌟
立川駅前こばやし内科・胃と大腸内視鏡クリニックです🏥✨
「最近、なんだかお腹の調子が悪い…🌀」
「便秘や下痢が続いているけれど、どうしたらいいのかがわからない…🌀」
このような、お腹のお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
便通異常は、多くの方が抱える問題でありながら、相談しづらいことも多いものです…💧
しかし、便通の乱れは、体が発している大切なサインです☝🏻
放置することなく、適切に対処することが健康維持の重要な鍵となるのです!🔑
そこで本日は、便通異常の原因、種類、改善方法、さらには医療機関での診断や治療法について詳しく解説をしていきたいと思います🍀日常生活の中でできる工夫もご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください*
【便通異常とは一体どのような症状のことを指す?】
便通異常とは、排便がスムーズに行えない状態や、便の形状や排便の頻度が正常範囲を外れている状態のことを指します。
代表的な症状として、以下のようなものがあります。
❶便秘
👆便秘は次のような症状があります。
・週3回以下の排便回数
→通常、排便の頻度が減少すると腸内に便が長く留まり、硬くなる傾向があります
・硬い便や小さくコロコロとした形状の便
→水分が不足した便が硬くなり、排出が困難になります
・排便時に強くいきむ必要がある
→腸の動きが鈍い場合や便が硬い場合、排便に過度の力が必要になることがあります
・排便後のスッキリ感がない(残便感)
→便が完全に排出されないと感じることがあります
👆便秘症状の原因として考えられること
・食物繊維や水分の不足
・運動不足
・ストレスや生活習慣の乱れ
・甲状腺機能低下症や糖尿病などの基礎疾患
・一部の薬剤(鎮痛薬、抗うつ薬など)
👆便秘への対処法
・食生活を改善し、水分を十分に摂取する🥛
・日常生活の中に適度な運動を取り入れる👟
・必要に応じて医師の指導のもとで便秘薬を使用する💊
❷下痢
👆下痢は次のような症状があります。
・1日に3回以上の水様便
→腸の動きが活発になりすぎると、水分が吸収される前に便が排出されます
・急な便意を感じる
→生活の中で突然の便意が襲い、トイレを急ぐ場面が多くなります
・排便時に痛みを伴うことがある
→腸が炎症を起こしている場合、排便時に痛みを感じることがあります
👆下痢症状の原因として考えられること
・感染症(細菌、ウイルス、寄生虫)
・食物アレルギーや不耐症(乳糖不耐症など)
・ストレスや自律神経の乱れ
・炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)
👆下痢への対処法
・水分補給を心掛け、脱水状態を防ぐ🥛
・刺激の強い食品やアルコールを避ける
・長引く場合や血便がある場合は早めに医師に相談をする👨⚕️
❸便秘と下痢の繰り返し
👆便秘と下痢を繰り返す場合、次のような症状があります。
・一時的に便秘が続いた後、突然下痢になる
・腹痛や不快感が排便で和らぐ
・排便パターンが一定でない
👆便秘と下痢を繰り返す場合の対処法
・食事内容を記録し、症状を悪化させる食品を特定する
・ストレス管理やリラクゼーションを日々の生活の中で心掛ける
・医師の診断を受け、症状をコントロールする薬を活用する
❹その他の症状と注意が必要なケース
便通異常に以下の症状が伴う場合、重大な疾患の可能性があるため注意が必要です⚠️
・便が細くなる(鉛筆状の便)
→腸に狭窄がある場合に見られることがあります
・血便や粘液便🩸
→消化管の炎症や腫瘍、痔などが原因として考えられます
・腹痛や膨満感
→腸閉塞や腫瘍、消化不良などが原因の可能性があります
👆受診が必要なケース
・症状が1週間以上続く場合🌀
・血便や体重減少、発熱を伴う場合🩸
・50歳以上で突然便通が変化した場合
便通異常は、一見よくある症状ですが、その背景には生活習慣やストレスだけでなく、基礎疾患や重大な病気が隠れている可能性があります⚠️症状が長期間続いたり、日常生活に支障をきたす場合は、早めに専門医を受診することが大切です🏥🩺
【便通異常の種類別・主な原因】
便通異常の原因は、日々の生活習慣から重篤な病気まで多岐にわたります。
❶便秘の原因
・食生活の乱れ
→食物繊維が不足していると腸内の善玉菌の活動が低下し、便の量や柔らかさが減少します。
また、脂肪分や加工食品の過剰摂取は腸内環境を悪化させることがあります。
・水分不足
→十分な水分摂取がないと便が硬くなり、排便が困難になります。
特に高齢者では、口渇感が低下するため特に注意が必要です。
・運動不足
→運動不足により腸の蠕動(ぜんどう)運動が低下します。
特にデスクワーク中心の生活や寝たきりの方ではリスクが高まります。
・ホルモンの変化
→妊娠中は黄体ホルモン(プロゲステロン)の影響で腸の動きが鈍くなります。
また更年期には女性ホルモンのバランスの乱れが便秘を引き起こすことがあります。
・ストレスや精神的な要因
→ストレスが自律神経系に影響を与え、腸の動きを鈍らせることがあります。
特に長期的な緊張状態は便秘を悪化させる要因となります。
・薬の副作用
→一部の薬剤、特に鎮痛剤、抗うつ薬、制酸薬(アルミニウムを含むもの)などが便秘を引き起こすことがあります。
❷下痢の原因
・感染症
→細菌(例:サルモネラ、カンピロバクター)、ウイルス(例:ロタウイルス、ノロウイルス)、または寄生虫感染による腸の炎症が原因となります。
・食事の内容
→脂っこい食事や冷たい飲食物は腸を刺激し、下痢を引き起こすことがあります。
特に急激な食事の変化は腸内環境を乱す原因となります。
・アレルギーや不耐症
→乳糖不耐症や食物アレルギーが原因となる場合があります。
これらは特定の食品を摂取した後に急激な腸の動きとして現れることが非常に多いです。
・腸の炎症性疾患
→潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性疾患では慢性的な下痢が主な症状となります。
血便や腹痛を伴う場合は特に注意が必要です。
・ストレスや精神的な要因
→特に過敏性腸症候群(IBS)の患者さんでは、精神的なストレスが腸の異常な収縮を引き起こし、下痢につながることがあります。
❸病気が原因の便通異常
長期間続く便通異常は、以下のような病気の兆候である可能性があります。
・大腸がん・ポリープ
→便秘や血便がみられる場合、大腸がんやポリープの可能性があります。
早期発見のため定期的な大腸カメラ検査が重要です。
・痔
→痔による痛みや出血が便通に影響を与えることがあります。
・腸閉塞
→急激な腹痛や嘔吐を伴う場合、腸閉塞の可能性があります。これは緊急性の高い状態です。
・甲状腺疾患
→甲状腺機能低下症では腸の動きが低下し便秘を引き起こす一方、甲状腺機能亢進症では下痢が生じることがあります。
・糖尿病
→自律神経障害を伴う糖尿病では便秘や下痢の症状が現れることがあります。
【便通異常の改善方法、日常生活でできる対策】
①食生活の工夫🍚
・食物繊維を積極的に摂る
→野菜、果物、豆類、全粒穀物などが効果的です。
ただし、摂りすぎると下痢の原因になることもあるのでご注意ください。
・お食事メニューに発酵食品を取り入れる
→ヨーグルト、味噌、キムチなどが腸内環境を整えます。
・水分補給を忘れずに
→1日1.5~2リットルを目安に水分を取りましょう。
朝起きたらコップ一杯の水を飲む習慣もおすすめです。
❷運動を日常に取り入れる👟
ウォーキングやヨガなどの軽い運動が腸の動きを助けます。また、腹筋を鍛えることも効果的です。
❸ストレス管理
ストレスは腸の働きを乱します。趣味やリラクゼーション法、十分な睡眠を日々心掛けましょう。
❹排便リズムを整える
毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつけましょう。トイレでは焦らずリラックスすることが大切です。
【医療機関での診断と治療】
便通異常が長期間続く場合、背後に病気が隠れている可能性があります。
診察や検査、治療を通じて原因を特定し、適切な対処を行います。
❶問診と診察
医師は以下の情報をもとに診察を行います
・症状の内容(便秘、下痢、腹痛の頻度や持続期間)
・生活習慣(食事内容、水分摂取、運動習慣、ストレスレベル)
・家族歴(大腸がんや炎症性腸疾患の既往)
・使用している薬やサプリメント
❷便検査(必要に応じて)
・感染症の検査
→細菌やウイルス、寄生虫による感染症の有無を確認します
・便潜血の検査
→肉眼では確認できない潜血(微量の血液)を調べ、大腸ポリープやがん、炎症性疾患の兆候を探ります
❸内視鏡検査(大腸カメラ検査)(必要に応じて)
直腸から大腸全体を観察し、大腸ポリープ、がん、潰瘍、炎症の有無を確認していきます。必要に応じて、ポリープの切除や組織の一部を採取(生検)し、精密検査を行います。
❹その他の検査(必要に応じて)
・画像診断
→CTやMRIを用いて腸の構造や周囲の臓器の状態を確認します
・血液検査
→貧血や炎症反応、甲状腺ホルモンの異常を調べます
❺治療法
主に食事療法や薬物療法が行われます。
・食事療法
→医師の指導のもと、食物繊維や発酵食品の摂取量を調整します
・薬物療法
→医師の指導のもと、症状に適したお薬を服用し改善を試みます
❻根本原因の治療
便通異常の原因が特定の病気に関連している場合、その治療が必要となります。
・感染症
→抗生物質や抗ウイルス薬を使用します
・炎症性腸疾患
→潰瘍性大腸炎やクローン病では、免疫抑制剤や抗炎症薬が用いられます
・大腸ポリープやがん
→ポリープの切除や、がんの場合は手術、化学療法、放射線療法が選択されます
・内分泌疾患
→甲状腺疾患や糖尿病が原因の場合、それに応じた治療を行います
・生活習慣の改善
医師の指導のもと、食事や運動、ストレス管理の習慣を改善し、便通の正常化を目指します。
【最後に】
便通異常は、デリケートな問題であるため、恥ずかしさから相談をためらってしまう方も非常に多くいらっしゃいます…💧しかし、便通の乱れは健康全般に大きな影響を及ぼす可能性があり、体が何かを知らせている重要なサインであることを忘れてはいけません!
日常生活の工夫(食事や運動、ストレス管理など)を通じて改善が期待できる場合もありますが、症状が長引いたり、痛みや血便といった異常が見られる場合には、早めに医療機関を受診することがとても大切です☝🏻
「誰もが経験することだから…」と一人で抱え込まず、専門医に相談することで、早期発見・早期治療が可能になります。
便通は健康状態を映し出す鏡でもあり、腸の調子が整うことで、体全体の調子も向上し、快適な毎日を過ごせるようになります。便通異常でのお困りごとがございましたらぜひ一度当院をご受診ください*